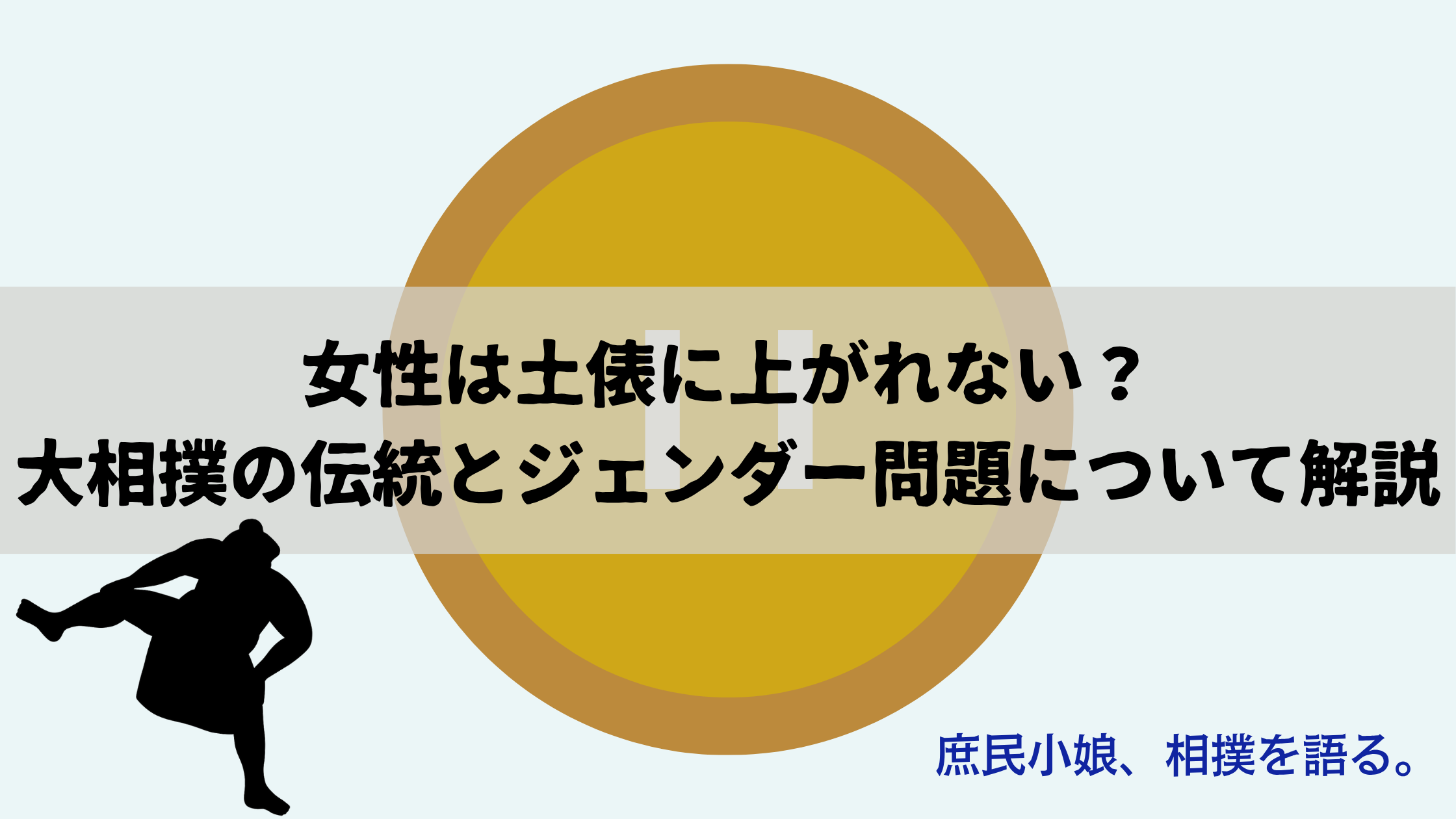近年、数々の相撲部屋YouTubeの台頭によって、大相撲を楽しむ女性ファンの姿がますます顕著になりました。
一方で、大相撲では「女性は土俵に上がれない」というルールがあることをご存知ですか?
よくよく注目してみると、力士の断髪式の際には該当力士の奥様など、女性の方がハサミを入れる際に土俵には上がらずに近くの台に上がっているのがお分かりいただけると思います。
大相撲の世界には長らく守られてきた伝統が数多く残っていますが、その背景には時代とのずれやジェンダー問題を含む議論もなれています。
本記事では、大相撲における「女性禁制」の歴史と現在の女性ファンの増加について考えていきたいと思います。
大相撲と「女性禁制」──なぜ土俵に上がれない?
大相撲の土俵は、長年にわたって「神聖な場所」とされてきました。
しかし、「女性を土俵に上がらせない」という慣習がどのように神聖な場所を保つことへとつながっていくのでしょうか。
相撲協会はこの慣習について、相撲の起源が神事にあることや、力士(男性)が命をかけて戦う神聖な場であることを理由に挙げており、「女性差別の意図はない」と説明しています。しかし、この「伝統」はどこまでが本来の信仰や習俗に基づくものなのかという点には、歴史的にも議論があります。
たとえば、近代以前の民間相撲や神社の奉納相撲では、女性の参加が完全に否定されていたわけではなく、地域によっては女性も土俵に関わっていたという記録があります(※読売新聞コラムより)。実際に現在のように「女人禁制」が固定化され、厳格に適用されるようになったのは、江戸時代以降、特に近代に入ってからだともいわれています。
現代社会においては、伝統と多様性の尊重のバランスが求められています。2018年には、舞鶴市で土俵上で倒れた市長を救助しようとした女性看護師に対し、「土俵から降りてください」と場内アナウンスがされ、相撲協会はこれを「不適切だった」と認める事態も起こりました。
ここまででわかることは、「女人禁制が最初から存在していたわけではない」、「土俵が男性が命をかける場所で、さらに相撲が神事に関わることが理由で女性は土俵に上がらせてもらえない」の2つです。
次の見出しでは相撲の伝統と現代社会のギャップについて触れていきます。
伝統文化と現代の価値観の”ギャップ”
ジェンダー平等が当たり前とされる現代において、「女性は土俵に上がれない」という慣習は、多くの人に違和感を与えています。たとえば、2018年に宝塚市の女性市長が相撲の土俵であいさつをしようとした際、日本相撲協会から「土俵の下からお願いします」と伝えられたことは、大きな議論を呼びました。この対応に対しては、「時代錯誤だ」という批判が出る一方で、「伝統を守るべき」という声もあり、社会の中でも意見は分かれています。
守るべき伝統も先ほど触れたように、「意外に近代に入ってから定着したものだった」というパターンがあります。つまり、どこからどこまでが「伝統」で、どこからが「伝統」という名の時代遅れな慣習なのかが曖昧な可能性があるということです。
このように、大相撲の「伝統」と現代社会の「ジェンダー平等」という価値観の間にはいまだに溝があります。土俵の女人禁制やセレモニー参加の制限といった問題は、現代社会において見直しを迫られる場面も多く、違和感を覚える人がいるのも事実です。
しかし、大相撲は今多くの女性ファンの支持を集めています。女人禁制と女性ファンの増加。一見矛盾しているように見えますが、筆者は全く矛盾ではないと考えます。次の見出しでは近年の女性ファン増加について詳しく掘り下げていきたいと思います。
YouTubeで広がる”推し力士”文化
近年、大相撲の人気を支えているのは、、相撲部屋によるYouTubeチャンネルと言っていいでしょう。稽古の様子や日常生活を発信する動画は素朴で飾らない魅力があり、さらに幕下の力士たちの苦悩など、普段テレビに映らない光景がリアルに感じられます。そのため、YouTubeで知れ渡った力士は、たとえ幕下以下の力士であっても国技館など会場から大きな声援が飛ぶことも少なくありません。
興味深いのは、この新しい人気の波が、土俵上の「女人禁制」とはあまり関係していない点です。伝統に対する違和感はあっても、それとは別の次元で、力士個人の人柄や仲間とのやりとりに心を動かされている。そうした“近さ”が、大相撲をより身近な存在に変えつつあります。
または単純に、「女性ファン」が「土俵上の女人禁制」に直接触れることがあまりないことも挙げられます。ファンが断髪式で鋏を入れることはまずないでしょう。「大相撲の問題だとは分かっていても、まぁ私には関係ないしな」という方や、そもそも大相撲が女人禁制の文化を持っているということがわかる光景を見たことがないので実感が湧かないという方もいらっしゃると思います。
このようなことから、女人禁制の継続と女性ファンの増加が両立できているわけがわかるかと思います。
大相撲とジェンダー平等の”これから”
大相撲における女人禁制は、宗教的・伝統的な慣習に基づくものとして長く続いてきました。
しかし、現代社会では、スポーツや公共的な場におけるジェンダー平等の実現が強く求められており、大相撲も例外ではありません。
伝統の継承と社会の価値観の変化の間で、組織としての姿勢が問われています。
しかし、大相撲における女人禁制が見られるケースとしては「女性が土俵に上がれない」くらいでしょうか。何が言いたいのかというと、「組織が急改革を要する問題と判断していない可能性があるのではないか」ということです。
断髪式、地方巡業の女性の挨拶、女性看護師の介抱など、「あぁ、やっぱり相撲って女人禁制の文化なんだな。時代遅れだなぁ」と思わせながらも、そう思うのは一瞬。
長期的な問題になりづらいのではないかと筆者は考えます。
とはいえ、土俵上で倒れた方を女性が介抱することを止めさせるような指導がなされてしまっていることは見過ごせません。
指導の行き渡り、緊急時のマニュアルなど見直すべき点は多々あります。その中で、結果的に時代に即した運営のあり方が求められるのではないでしょうか。
小娘小話:ファンの増加、マナーの低下?
今回は女性ファンの増加を取り上げましたが、男女関わらずファンの熱量が高まるにつれ、場所中のマナーに関する課題も出てきています。例えば、入り待ちでのマナーについてです。
「入り待ち」とは、力士が本場所の会場に到着するのをファンが入口付近で待ち、姿を見たり、声をかけたりする行為のことです。人気力士の登場を楽しみにしているファンが多く、写真撮影やサインを求める場面も見られます。
しかし、入り待ちでのサイン・写真撮影などはこれから命懸けで”戦う”力士にとって集中力が切れてしまう原因になります。「今日の取組の勝敗で関取になれるかどうかが決まる」というような幕下力士などは、特に精神統一を行う必要があるかもしれません。
このようなことから、入り待ちでの対応の仕方についての相撲部屋のYouTubeチャンネルから動画が公開される事態にもなりました。
こうした問題は、スポーツとしての大相撲と、エンタメ的な“推し文化”の狭間で、ファン自身もバランスを考える必要があることを示しています。
ちなみに筆者はこれまで力士が目の前に来たことはあっても、人見知りを発揮してしまい(地方巡業で推しの明生関が目の前を通過した時、声も出せずただ後ろ姿を目に焼き付けていました)、何もできないタイプなので迷惑をかけるようなファンになっていないと思いますが、あくまで力士たちはYouTuberやタレントではなく「スポーツ選手」であることを強く理解する必要があると感じました。