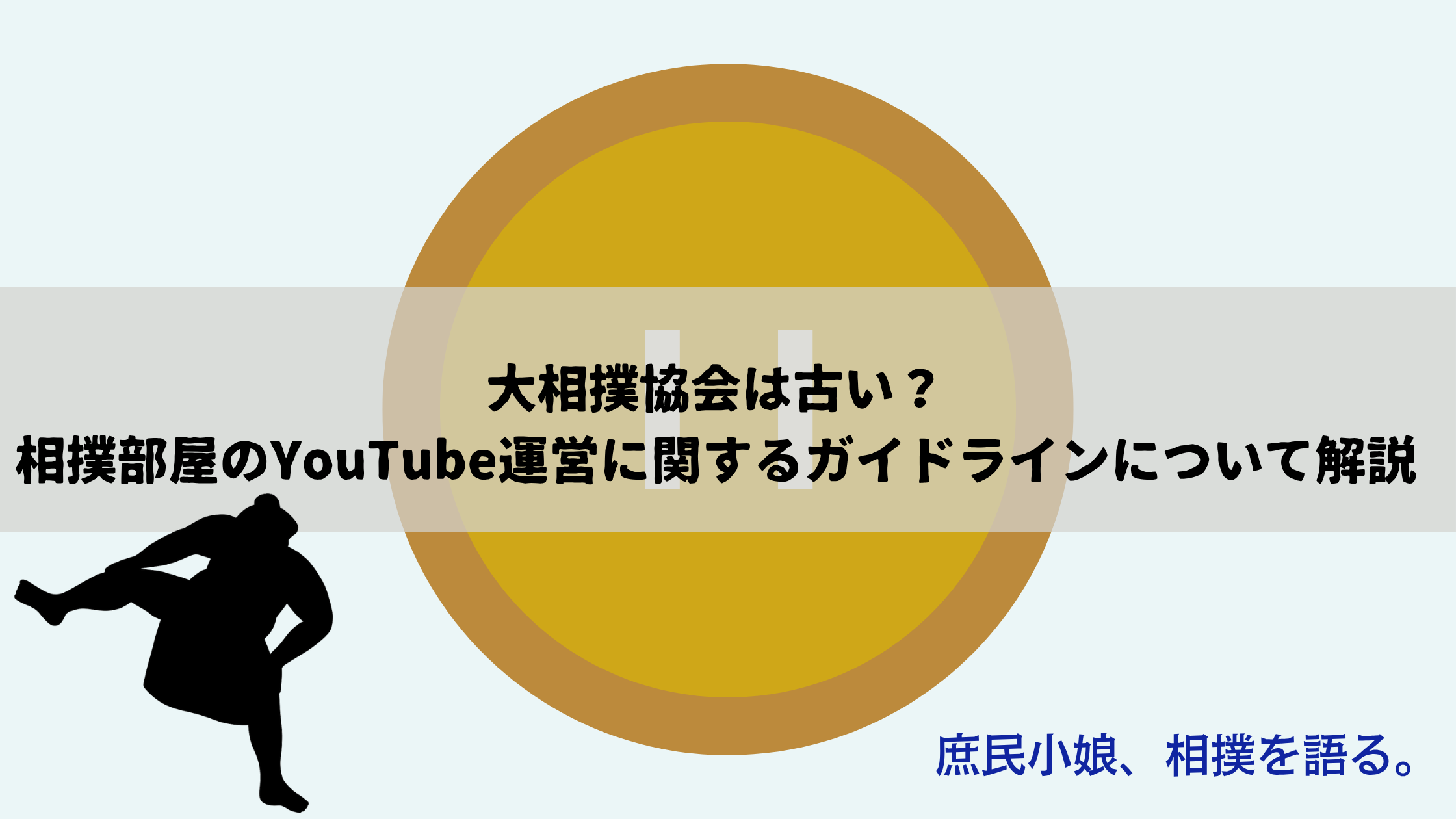大相撲に興味を持つ方の中には、「相撲部屋のYouTubeを見て好きになった!」「昔から相撲は見ていたけど、YouTubeを通じて幕下以下の力士にも注目するようになった!」という方もいらっしゃるかもしれません。
現に相撲協会の公式チャンネル「日本相撲協会公式チャンネル」の登録者数は29.2万人(2025年5月27日現在)であり、各相撲部屋のYouTubeチャンネルも積極的に動画をアップしています。
そのような中、日本相撲協会は4月10日付けで各部屋へ「YouTube運営ガイドライン」が通達されました。
今回のブログでは、このガイドラインの内容に触れた後に、「ガイドライン通達後、各部屋のYouTubeチャンネルはどのように変わっていくのか」という考察を女子大学生の大相撲ファンである筆者なりにお伝えします。
どこまでOK?YouTubeガイドラインの中身を読み解く
日刊スポーツの記事によると、
①本場所中の動画公開禁止
②生配信禁止
③相撲部屋同士のコラボ禁止
④投げ銭禁止
⑤メンバーシップ機能禁止
⑥企業案件禁止
さらには「大食い」「大袈裟な音声効果」「悪ふざけ」など相撲文化や力士の品位を損なう過度な演出がNGとなっています。
さらに違反した場合のペナルティとして「相撲部屋の一切のSNS禁止」が設けられています。
内容をざっと見てみると、「禁止事項ばっかりじゃないか!」「せっかく若者ファンを増やすチャンスを逃すのか!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実際にSNS上の反応では若者への相撲の普及について影響が出るのではないかという懸念や、テレビでの大食い企画への参加とガイドラインとの矛盾について指摘する声が上がっています。
そもそも、なぜこのようなガイドラインが出されることになったのでしょうか。項目を一つ一つ整理しながら考えていきましょう。
※ここからは筆者の憶測による記述が多く含まれます。
①本場所中の動画公開禁止
この項目は読者の方も想像がつくかもしれませんが、「力士が本場所に集中するため」ではないかと筆者は考えます。
本場所中に動画を公開してしまうと、コメント欄やSNSの書き込みが力士の集中をかき乱す恐れがあります。「YouTubeの企画でこんなことしてたから今場所負け越したんだ!!」などと書かれては困りますよね。
もちろん、これは本場所中以外での動画公開でもあり得る例ですが、本場所中の動画公開で起こった方が取組に支障が出るのは確かです。
②生配信禁止、④投げ銭禁止、⑤メンバーシップ機能禁止、⑥企業案件禁止
この4つはおそらく、「協会を通さずに金銭や報酬をもらうんでない」というメッセージが込められていると思います。
相撲協会は自分たちのような「大きな組織」の知らない間にYouTubeチャンネルという「小さな組織」が勝手に動くのを阻止したいのかもしれませんね。
③相撲部屋同士のコラボ禁止
これも賛否両論ありそうな項目ですね。
「土俵に立てば敵。仲睦まじい様子なんていらん」
「部屋の垣根をこえての交流も見たい!」
他にも様々な意見あるかと思いますが、おそらく協会はエンタメとしての大相撲よりスポーツとしての大相撲を優先したのではないでしょうか。
この6つの項目に共通することは、「彼らはYouTuberの前に力士である」という思いが込められているような気がします。
ガイドラインは時代遅れ?
このガイドラインが発表されてからのSNSの反応は賛否両論あります。
中には「こんな規制ばかりでは相撲協会は廃れていく!」と言いたいんだろうな、というコメントも見受けられます。
しかし、この規制が相撲部屋のYouTubeを大きく変えるとは筆者には見えませんでした。
考察:相撲部屋のYouTubeはそこまで変わらないのでは?
今回のガイドラインは、簡単に言ってしまえば「本場所中に余計なことをしたり、金を稼いだり、部屋同士のコラボをしたり、大袈裟な効果を加えるのは禁止」という相撲協会からの通達です。
逆に言えば、「本場所中に余計なことをせず、金を稼がず、己の部屋のみで質素な動画を作る」ことには全く問題はないわけです。
相撲部屋のYouTubeの中でもダントツの人気を誇る二子山部屋のYouTubeは、本場所中の投稿はされておらず、メンバーシップ機能などもなく、ただひたすら稽古・料理・食事風景を字幕のみの動画でチャンネル登録者数50万人を目前としています(2025年5月28日現在)。
要は、ガイドラインに規制されても視聴者を惹きつける動画は作れるわけです。
同じような編集方法で動画をあげているチャンネルに立浪部屋が挙げられますが、動画投稿を開始して半年足らずで7万人を突破しています。二子山部屋がYouTubeを早くから始めたから登録者数が伸びているだけではなく、早かれ遅かれ興味を持たれるのは変わりありません(立浪部屋は豊昇龍が横綱に昇進したこととYouTubeチャンネル開設がベストタイミングだったこともありますが)。
また、エンタメ要素の強いチャンネルだと伊勢ヶ濱部屋が挙げられますが、大食い禁止になることがどこまで響くか(多分そこまで響かないでしょうが)などの多少の懸念点はあるものの、決まり手解説や部屋内運動会など、他の相撲部屋のYouTubeとはいい意味で差別化を図っているように思えるので、特段動画内容が変わるとは思えません。
ガイドラインで規制されても、相撲部屋の個性が失われることはありません。
関取が多い伊勢ヶ濱部屋、横綱の土俵以外の一面が見れる立浪部屋、有望な若手が増えている二子山部屋、伸び盛りの力士を持つ秀ノ山部屋など、それぞれの部屋の特徴を捉えたYouTubeの動画が視聴者の興味を引きるけることに変わりはないのではないかと、筆者には思えました。
小娘小話:ガイドラインは力士を守るため?
少しガイドラインについて踏み込んで考察してみると、視聴者からお金を巻き上げることを禁止している点に関しては、「力士の過度なタレント化・アイドル化を抑制したいのではないか」とも思われます。
もし「投げ銭」なるものが可能になってしまった場合、コメント欄に「◯◯さんのプロテイン代の足しにしてください!」など、個人向けの投げ銭が可能になる、ということになります。
プロテイン代ならまだマシな方ですが、それが行き過ぎた額になるとトラブルになりかねません。また、「◯◯にはたくさん投げ銭が来るけど、◻︎◻︎は全然人気ないな!」などの新たな誹謗中傷が生まれることもあるかもしれません。
また、生配信を可能にすれば力士のプライベートな空間をリアルタイムで全世界に発信できてしまうことになります。生配信にある物が映って勝手に「彼女がいるのでは?」などの相撲に関係のない憶測が広がってしまうことも考えられます。
このようなことから、ガイドラインはある側面では力士を守る目的も果たしていると言えるかもしれませんね。