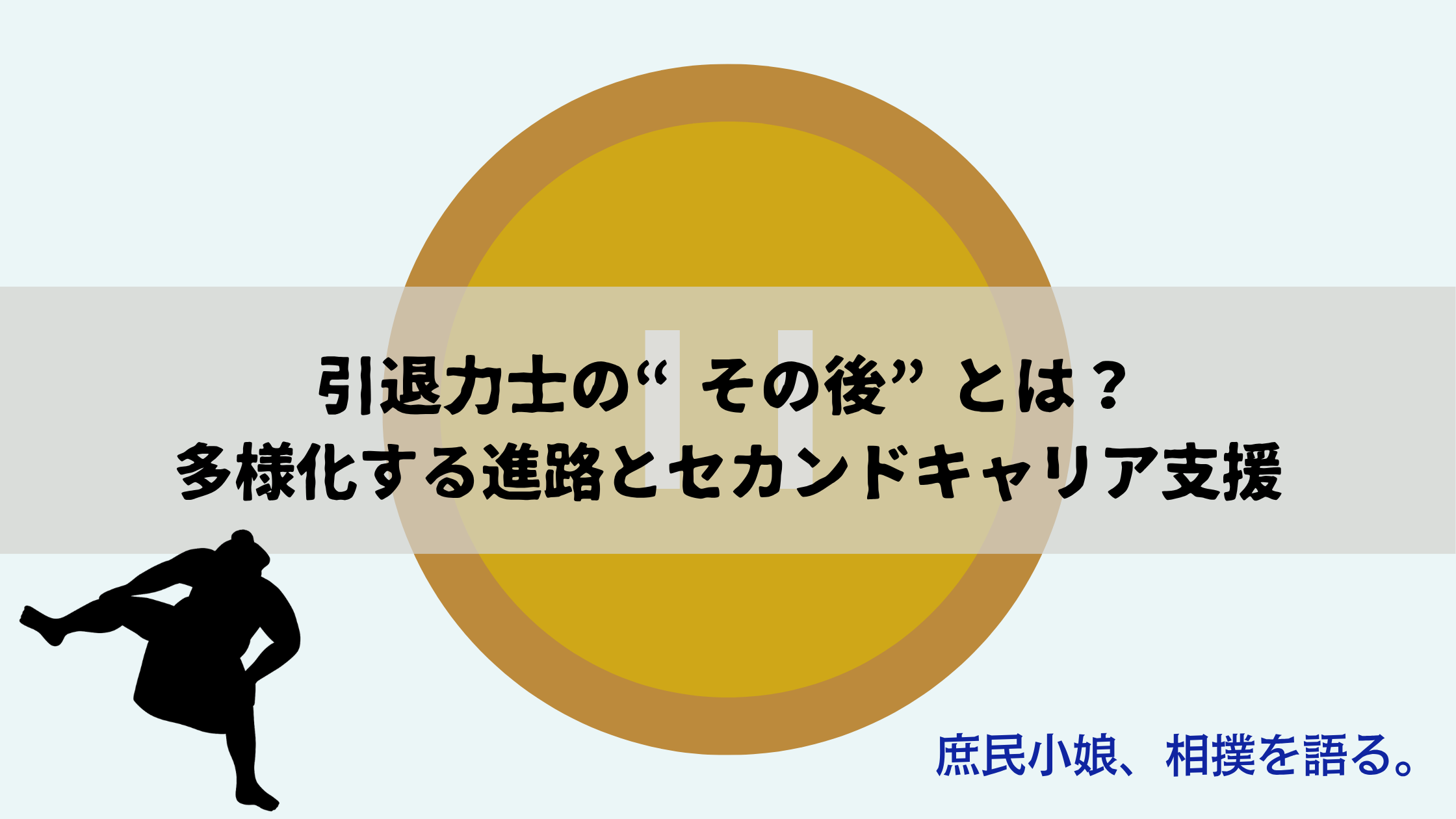現役生活を終えた”元力士”は、その後どんな人生を歩んでいくのでしょうか。
現役生活は長い人でも20年ほどでしょう(玉鷲は現役生活21年目に突入していますが)。大学卒業後、プロの世界に進んだ力士はわずか10年足らずで引退…なんてことも不思議ではありません。
つまり、現役力士として土俵に上がっている年数よりも元力士として土俵を下りて生活する年数の方が長い可能性が非常に高いということです。
引退した力士は相撲界に残って親方として活動する人もいれば、全く別の世界に飛び込む人もいます。最近では一般企業への就職・飲食店の開業・タレント活動など、その進路はどんどん多様化しています。
しかし、セカンドキャリアを華々しくスタートできるのはほんの一部。現役時代に華々しい結果を残せた人に限られる場合がほとんどです。
この記事では、元力士の引退後のキャリアとその裏側にあるセカンドキャリア支援について考えていきたいと思います。
※これから引退した力士の方々の名前を出させていただきますが、現役時の四股名(敬称略)で書かせていただきます。ご了承ください。
進路①:親方として相撲協会に残る
この進路がイメージからすると一番メジャーかもしれません。
現役を引退した後に相撲協会に残り指導者になるためには「年寄名跡(みょうせき)」という特別な資格が必要です。
無限に年寄名跡を増やせるわけではなく、現在は105個と限定されています。つまり、空きが出ないと新しく年寄を名乗ることはできません。しかも多くは売買や貸し借りで成り立つことが多く、このことから「親方株」「年寄り株」と呼ばれることもあります。
ここからわかることは、引退力士が親方になるためには実力だけではなくお金や引退のタイミング、人間関係が必要であるということです。
また、親方になるためには「日本国籍」を有することが条件です。
先日、横綱豊昇龍が日本国籍を取得したことが話題になっていましたが、「立浪部屋を継承するのでは?」という期待・疑問から話題になったのかもしれません。
親方として残っている元力士として、照ノ富士や貴景勝など横綱・大関経験者をはじめ、妙義龍や北勝富士などベテラン力士として活躍した方も挙げられます。
進路②外部指導者として相撲界に関わる
「年寄名跡がなくても相撲を支えたい」──そんな元力士もいます。
例えば、大島部屋の日高コーチをご存知でしょうか。
彼は最高位幕下29枚目の元力士(春日龍)です。現役時代、弓取りを務めたこともあります。現在は大島部屋でコーチとして弟子への指導を行なっています。
形は外部指導者となるのでしょうが、このような存在は相撲界ではまだまだ新しいです。しかし、年寄り株継承の困難さから見ても、このようにコーチとして雇われるのは「引退後も相撲協会に関わっていきたい!」という力士にとって嬉しいことではないでしょうか。
進路③:飲食店経営
相撲部屋では、幕下以下の力士たちが交互に昼ご飯と夜ご飯を「ちゃんこ番」として作ることが多いです。
その時の知識を活かして、引退後に飲食業を始める元力士も少なくありません。
例えば元小結の松鳳山は、船橋に「焼肉・ホルモン 松鳳山」という焼肉屋をオープンしており、その傍らABEMA大相撲で解説を務めるなど、精力的に活動しています。
部屋の文化やこだわりが詰まった「食」を活かしたセカンドキャリアは、まさに元力士ならではの選択肢といえます。
進路④一般企業で再スタート
引退後に再就職して一般企業に勤める人もいます。
最近で言うと元小結の阿武咲が、馬油を使った石鹸や化粧品などの美容部品を扱う会社に一般就職しました。SNSに白衣姿で顕微鏡で何やら観察している様子などがアップされ話題になっていましたよね。
他にもYouTubeで大人気の二子山部屋に所属していた元幕下の舞蹴は、国家資格が必要な柔道整体師を目指して都内の専門学校に通うなど、「身体を支える仕事」として大相撲の経験を活かす仕事をしようと奮闘しています。
さらには体力勝負である介護職や、体育の教員など、大相撲での経験が間接的に役立つ職についてる方々が多く見られます。
進路⑤タレント・芸能活動
引退後もテレビやYouTubeなどで活躍している方もいます。
元関脇の豊ノ島や、元小結臥牙丸は、YouTubeで大相撲について発信する傍ら、ABAMA大相撲での解説も行なっています。
また、タレントではありませんがインバウンド向けの飲食店で力士としてのパフォーマンスをされている方もいます。ここ最近の外国人観光客増加でより相撲の文化を身近に知ってもらいたいという思いがあるのかもしれません。
力士のセカンドキャリア、相撲協会はどう考える?
幕内などで長い間活動しており、名が知れ渡っていた元力士もいれば、下積み期間に引退した力士もいます。
しかし、番付主義の厳しい大相撲界ですから、ほとんどの「元力士」が後者に当たるわけです。
さらに中卒で入門する力士もいます。いわゆる「叩き上げ」です。幕内力士だと錦木や隆の勝、明生などが該当します。
幕内で活躍できるようになれば良いですが、叩き上げ力士が全員関取になれるとは限りません。
最低限の義務教育・大相撲の知識のみで、急に一般社会に放り出されることになるわけです。
現役力士の寿命が長くなっていることも、一つの注目点です。
30代〜40代になって、「社会人1年目」として第二のスタートを切る勇気を持たなければいけません。
このような状況で、セカンドキャリアをサポートしていく体制が相撲協会にはあるのでしょうか?
結論:サポート体制はない。でも…?
結論から申し上げますと、相撲協会としてのサポートはないといいって良いと思います。
日本相撲協会自立就職支援相談室というものが設置されていますが、Googleで検索しても10年以上前の記事が多く、きちんと成り立っているのかどうかということまではわかりませんでした。つまり、十分ではありません。
しかし、相撲部屋によっては「セカンドキャリアのサポートと言えるのではないか」という活動をしています。
例えば立浪部屋では、中卒で入門した力士を対象に、通信高校で授業を受講して高卒の認定を取ることができるように勉強するという活動を行なっています。
中卒と高卒で何が変わるのかは詳しくないので触れませんが、現役中に少なくとも「机に向かって勉強する」という活動が起こるため、引退後に資格を取るときなどに役に立つのではないかと考えます。
また、相撲界から一般社会へ円滑に移行できるように、仕事探しから心のサポートまで幅広く行なっている「一般社団法人 力士セカンドキャリア推進協会」という団体もあります。
元力士の方が経営するこの会社では、介護職・飲食業・整体業など、各業界や職種への橋渡しを行なっています。
この活動は力士の引退後のキャリア形成において、新たな可能性を示していると思います。
しかし、もう少し相撲協会自体で何かできないのかな〜と個人的には感じました。
例えば、入門したばかりの力士たちが6ヶ月間通う「力士の学校」である相撲教習所では、基礎運動ののちに相撲の歴史・運動医学・書道などいわば「座学」の授業があります。
ここに、もう少し社会的な授業を取り入れても良いのかなと思います。授業を聞いていて興味が湧いて、引退した後にその分野を追求する…。少し夢物語ですが。
「現役時代に相撲以外のこと考えてちゃ強くならない!」と思われる方の気持ちもわかりますが、どう足掻いても引退の時は必ずやってきます。
そんな引退後の自分を想像する時間があってもよいのではないかなと思いました。
まとめ:土俵の上だけが人生じゃない
力士としての人生は短くても、その後には多彩な道が広がっています。
そしてどの道に進んだとしても、相撲で培った経験や精神力は必ず役に立ちます。
今後も、さまざまな「引退後の生き方」が生まれるはず。
土俵を下りた力士たちの第二の人生にも、ぜひ注目してみてください。
小娘小話:中継にチラッと映る”元力士”
大相撲中継では、花道(力士や行司などが支度部屋から土俵へ向かう通路)で警備をしていたり、審判として土俵のすぐ近くに座っていたりする”元力士”が、チラッと映る時があります。
「照ノ富士めっちゃ後輩の取組見てるじゃん!」「貴景勝痩せた?!」などとSNSで話題になることも。
そんな姿を見ると、「あぁ、元気そうでよかった。」と勝手に親心が芽生えてしまいます。
大相撲中継を見る際は、ぜひ土俵以外の場所も注目して見てみてくださいね。